現代でなぜ武道をやるのかという問いに対し、その答えは一人一人違っています。
修行年数によっても答えは変わってきますので、同じ人でもどの時期に
この問いをされるかで、答えは変わってくるでしょう。
しかし、最終的に辿り着く答えの一つは、この記事で書く内容なのではないかと私は思います。
私が武道を始めたきっかけは漠然と強くなりたいと考えたことでした。
その様に考え、武道を始めましたが、結局のところ身に付けた技を
使う場面に遭遇したことはありません。
もしもの時に備え、稽古を重ねるというのは大切なことです。
稽古していたおかげで危ない場面を切り抜けることが出来たという方も
いらっしゃることでしょう。
ですが、その様な人の数は多くないと思います。
技を使うのはあくまで最終手段で、身を護るということであれば、
実際に身に付けた技を使う状況にならない様に立ち回ることの方が大切です。
そうして考えると護身という意味で、武道をやる意味はあまり無い様に思えます。
おそらく、私と同じ様な動機で武道を始めた人の中には、年齢を重ねるにつれて、
私と同じ様なことを考え、次第に武道の稽古をやる意味を見失ってしまった人もいると思います。
私の場合は幸いにも、武道を修練することの意味を新たに見出す前に面白さの方が先立ち、
武道の稽古を続けることが出来ました。
途中でやる意味を見失い、辞めてしまうのは、非常に勿体ないことだと感じますので、
現在の私が辿り着いた武道をやる意味について、お伝えしたいと思います。
端的にいうと、武道は幸せに生きるために真っ当に生きる方法を学ぶものだと私は思います。
世の中で生きるために必要な能力とは何でしょうか?
私は、その一つはコミュニケーション能力だと思います。
武道では、礼儀が重んじられますが、稽古を通して幅広い年代の人と接し、
礼儀を学ぶことは、社会で生きるためのコミュニケーション能力を磨きます。
また、武道の技は奥深いところにいくにつれて、心の機微を察することが
大変重要となっていきます。
その心の機微を察する能力も人とのコミュニケーションには必要なものです。
そして武道では、自分を見つめ、反省し、律することが求められます。
稽古を重ねる中で、必ず壁にぶつかり、自分と向き合わなければいけない時がきます。
技の稽古は、ただ動作としてそれを学んでいるわけではありません。
心・技・体と言われますが、技(動作)だけでは、不完全です。
心と体も伴って、はじめて本当の技となります。
人と対峙することも、武道の技も本来は怖いことです。
その怖さを乗り越え、平常と同じ様に動く。
それが技には必要で、そのために心と体を磨きます。
自分と向き合い、正しく反省し、自分を律して良い方向に変える。
それが技の修練を通して、学ぶべきことです。
この様に書くと大袈裟に感じる方もいらっしゃると思います。
以前の私は、同じ様な話を聞いた時にそんな大層なものではないだろうと
心の中で思っていました。
実際にそんなことを学ぶことは出来ないのに、武道を美化しすぎていて、
仰々しく言っているだけだろうと考えていました。
しかし、稽古で自分の体が無駄に力み、技に失敗する原因を探ると
その時の精神状態が影響していることを認めざるを得ず、
自分の心が未熟であることを痛感しました。
そうして、日々稽古を重ねていると、自然と上記の考えに至りました。
自分の心と体に向き合うことで、自分を律し、変えていく。
それは武道で必要なことであり、武道意外のところでも役立つものだと感じています。
幸せに生きるためと前述しましたが、それは個人の幸せだけを追求するものではありません。
調和を以って、集団としての幸せも追求するものです。
些細なことで大怪我に繋がる武道の稽古は、お互いを労わることなく稽古することは出来ません。
一緒に稽古してくれる人が居てくれてこそで、自分勝手な一人善がりというのは、
武道からは遠いものです。
お互いに尊重し合いながら稽古をしていると、自分だけの幸せを求めることにはなりません。
お互いに笑顔で過ごせる様に尽力するのが当たり前となります。
ここまで武道から何を学ぶのかを書きましたが、では実際に武道の稽古をしている人が、
それを学べているのかというと多くの人は学べていないと思います。
武道をやることで人格形成に繋がるという人もいますが、
そうだったとしたら武道をしている人は皆、人格者となります。
しかし、現実には皆が皆、人格者というわけではありません。
私は、武道をやることで人格者になることも出来ると考えていますが、
それは正しく武道に取り組んだ結果です。
今回の記事で書いた、幸せに生きるために真っ当に生きる方法を学ぶというのも、
正しく武道に取り組まなければ、得ることの出来ないものだと思います。
正しい思いで正しく武道に取り組む、それが大切だと感じます。
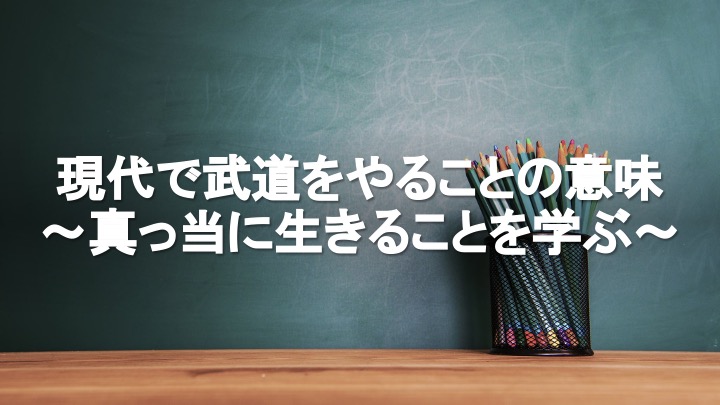


コメント