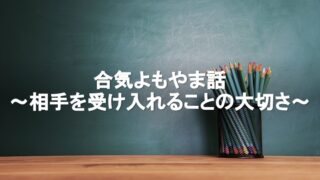 上達論
上達論 合気よもやま話〜相手を受け入れることの大切さ〜
武道では、よく相手を受け入れることが大切だと説かれます。それはなぜでしょうか?私も昔、師からその様に指導されましたが、その当時は意味が分かりませんでした。しかし、稽古を重ねるうちに、その意味の一端が見えてきました。相手を受け入れることの意味について、解説しています。
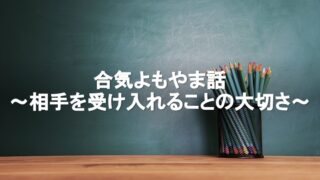 上達論
上達論 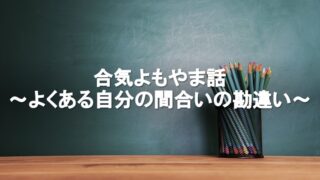 上達論
上達論 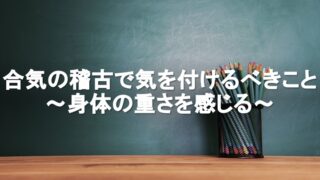 上達論
上達論 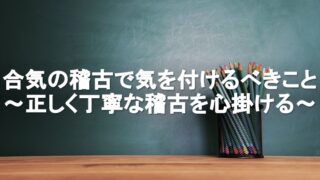 上達論
上達論 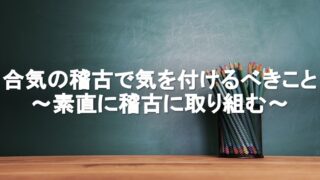 上達論
上達論 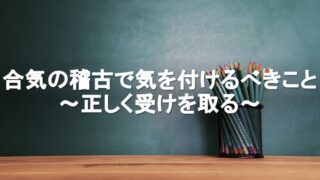 上達論
上達論 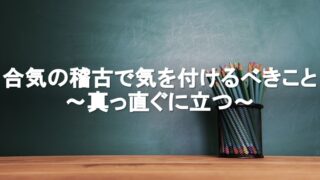 上達論
上達論 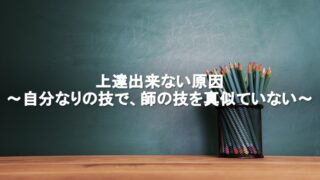 上達論
上達論 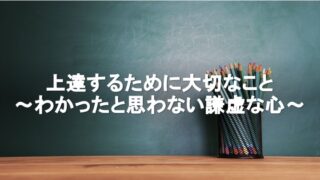 上達論
上達論 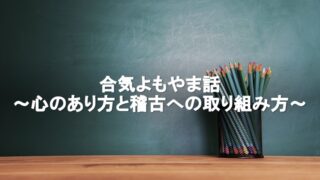 上達論
上達論