ふと思い立って、昔の稽古風景を撮影した動画を見ました。
それは私が入門して2年目のものです。
私の記憶では、技の術理は全く分かっておらず、
師の技を形だけ真似して一生懸命に稽古していた頃です。
てんで出来ていない状況を想像して動画を見始めましたが、見てみると悪くありません。
動画の動きを見る限りでは、技として成立している様に見えます。
しかし私の記憶では技が出来ているはずがなく、動画の状況は有り得ません。
動画を見て、私は2つのことを考えました。
一つは、動画で技の実際を判断することは難しいということ。
もう一つは、掛かり稽古の難しさについてです。
当時の私が技が出来ているはずがないのに、動画を見ると技が出来ている様に見える。
その原因は掛かり稽古にあります。
私が学んでいる流派では、掛かり稽古主体の稽古をしていますが、受け(技を掛けられる人)が
技の流れに合わせて受身を取ると技がきちんと掛かっている様に見えます。
合気’の技で投げられるというのは、言い方を換えると
受けが耐えられないレベルで’合気’が掛かっているということです。
’合気’の掛かり具合にも段階があり、浅かったり深かったりします。
’合気’の掛かりが浅いと、技を掛けられても平然と耐えることが出来ますし、
’合気’の掛かりが深いと、技を掛けられると耐えることが出来ずに投げられてしまいます。
このへんが厄介で、’合気’の掛かりが浅くても受けにはそれらしい反応が出ており、
技に合わせて受けが受身を取ると技が出来ている様に見えてしまいます。
そのため、映像だけで’合気’の技が出来ているかを判断するのは、私は難しいと考えています。
技に要求される動きをしているかという点や姿勢、細部の意識の持ち方などで、
実力を推測することは出来ますが、自分で技を受けないと最終的な判断は出来ません。
また掛かり稽古の難しさも、見た目で技の出来が判断出来ないということに関係します。
技がきちんと掛かって受けが受身を取るのであれば良いのですが、
中途半端な技で受けが受身を取っても分かりません。
中途半端な技で受けが受身を取っていると、取り(技を掛ける人)は自分の技が
出来ていると勘違いしてしまいますので、勘違いが起きない様に受けは受身を取らずに
次の人にすぐ代わるなどの工夫が必要となります。
しかし、技の出来を判断するためには、受けが正しく取りに掛かっていくことが必要なため、
それが出来ないうちは判断をすることが出来ません。
とりあえず受身を取るという方向に行かざる得ない事情もあります。
これは稽古に参加している人の習熟度にも影響される話なので、
一律に掛かり稽古のやり方を決めることは不可能です。
おそらく掛かり稽古は技の出来に関わらず受身を取るという場合と技が掛かっていなければ
受身を取らないという場合の2つを揺れ動くものなのだと思います。
技の出来に関わらず受身を取ることを続けていると技が出来ているか分からなくなりますし、
技が掛かっていないと受身を取らないということを続けていると、取りは迷いが出て、
余計に技が出来なくなる悪循環に陥ります。
どちらの場合もデメリットがあります。
’合気’の技を身に付けるために掛かり稽古を行なっている理由は、間断なくテンポ良く受けが取りに
掛かっていくことで思考を介在させずに技を繰り出す癖をつけるためです。
思考が介在しないことで、自然な動きとなりやすく、またその動きを咄嗟に行うことが
出来る様になります。
それを狙って掛かり稽古を行なっているわけですが、技の出来が自分で判断出来なくなる様では
元も子もありません。かと言って、技がきちんと掛からないと受身を取らないということを
続けていては、稽古の流れが止まり、掛かり稽古になりません。
掛かり稽古にはメリットとデメリットがありますが、メリットを享受するためには、
稽古に参加している人の習熟度に合わせてバランスを取り、その都度受けの取り方を
調整していくことが必要なのだと思います。
一様に稽古をしていては駄目だというところに、掛かり稽古の難しさがあると感じます。
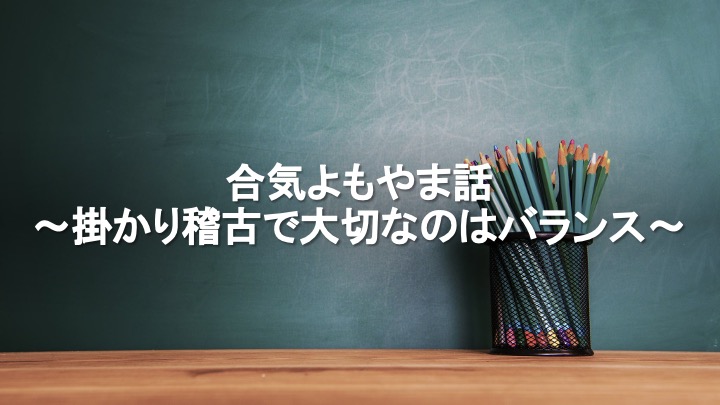


コメント