自分の身体を観察しながら木刀で素振り等をするとよく分かるのですが、
自分の身体で上手く使えていない部分というのは、
大きなブロックとしてしか使えていないことに気付きます。
例えば、肩の動きにしても、木刀の振り上げ・振り下ろしの際に理想としては、
滑らかに動いてほしいのですが、その様には動かず、
動かない部分は動かないまま(固めたまま)、動かしています。
無駄に力が入っているために、細かく使うことが出来ず、
その様な動きになっているわけですが、武道・武術の稽古というのは、
身体を開発して大きなパーツでしか動かない部分を小さなパーツで
動く様にしていく作業だと私は考えています。
大きなパーツでしか動いていない部分は、
視覚的にも触覚的にも分かりやすく、
相手に察知されやすい動きになるため、
可能な限り細かなパーツで身体を動かすことが理想です。
細かなパーツで身体を動かすことで動きが滑らかとなり、
相手に動きを察知されにくくなるだけではなく、
相手に力を流す様なイメージで力を伝えることが可能になるからです。
はじめて行う動作の場合、動きに慣れていないために
ぎこちない動きになるのですが、普段行っている動作でも
無駄な力が入っているために動きがぎこちなくなっていることがあります。
通常は、動作を繰り返すうちに動きがスムーズになっていきますが、
ともすれば、無駄な力が入った状態で動かすことに慣れ、それが癖になるわけです。
本人としては、その部分に違和感を持つことも無くなるため、
滑らかに動いていないことに気付かなくなります。
そのため、武道・武術の稽古の一環として、日常の動作で無駄に力が入って、
大きなパーツで動いている部分がないか、見直すことは大変重要なことです。
これは道場で行う稽古では出来ない部分となりますので、
各人がそれぞれで行う作業になりますが、これをやれているかどうかが、
その後の上達の仕方を大きく左右するように思います。
また、自分の身体を観察していると気付きますが、
その時持っている感情により、身体の状態は大きく変わります。
怒っていたり、緊張しているとそれだけで無駄に力が入っています。
そのため、自分の身体を思う様にコントロールするためには、
精神を一定に保つ様に心掛ける必要があります。
最近つくづく思うのですが、武道・武術の稽古は自分を観察し、
対話することが大切だと感じます。
精神的にも肉体的にも自分がどういう状態なのかを常に観察して、
それをもとに修正していかないといけないからですが、
その様な作業を行わなければいけないからこそ、
成長することが出来、武道は「道」に通じるものなのだと思います。
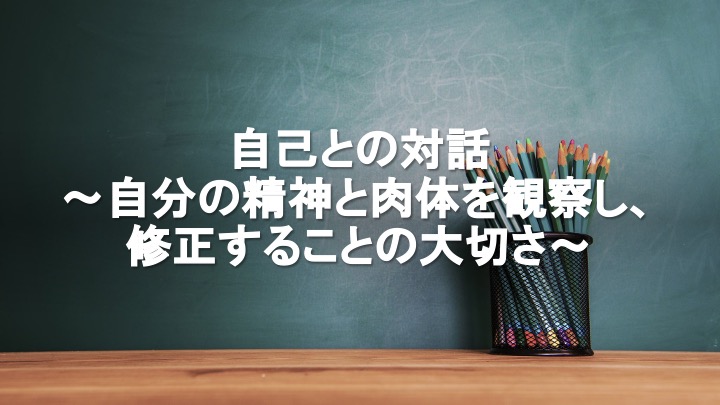

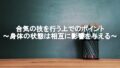
コメント