今まで’合気’を身につけるために稽古を続けてきましたが、
どのような稽古をしていけばよいのか見えてきたので、
今日はそのことについて書きたいと思います。
長年稽古をしても’合気’が身につかなかったわけですが、
その原因は、自分の身体をルールに沿って動かすことが出来なかったためでした。
’合気’の技を相手に掛けるためには、自分の身体を一定のルールに沿って、
動かす必要がありますが、そのルールから外れた動きをずっとしていたわけです。
入門して数年は、身体の動かし方のルールが分からず、四苦八苦しましたが、
稽古を重ねると次第に、そのルールが分かってきました。
現在もそのルールの理解を深め、ルールに沿った身体の動かし方をするように
稽古をしていますが、振り返るとルールの理解がもっと浅い時分であっても
もう少し’合気’の技が出来てもおかしくなかったと思います。
長年、’合気’が身に付かなかったといっても、全く技が掛からなかった
というわけではありません。
1回の稽古のうちに何回か掛かりますが、そこから技を成功する頻度は上がらず、
また、自分で意図して技を掛けられているという実感がなかったために
全く前進している気はしませんでしたが、今考えると’合気’を掛けるための
ルールに沿った身体の動かし方に近いことはやっていました。
ただ、少しですがそこから外れていたために、結果としてルールに沿った
身体の動かし方になっておらず、技が掛かっていませんでした。
では、なぜルールに沿った身体の動かし方を外していたかというと、
相手に合わせて動きを変えてしまっていたからです。
これには、意識的な部分と無意識的な部分の二つがあります。
意識的な部分でいうと、相手の掴み方の癖等を知っている場合は、
その掴み方に合わせる様に身体の動かし方を変えていました。
しかし、身体の動かし方のルールがまだはっきりと理解出来ていない頃でしたので、
相手の癖に合わせて対応しているつもりで、結局はルールから外れた
身体の動かし方になっていました。
無意識的な部分でいうと、自分より大きな相手であったり、力の強い相手、
苦手な相手の場合は、無意識に力が入り、ルールから外れた動きとなっていました。
合気系の武道では、取りと受けに分かれて掛かり稽古を行います。
そして、相手に手首を掴まれたり、襟を取られたりして、技の稽古を行っていきます。
人により、立ち方も違えば、掴み方も違いますので、
それに合わせて調整することは必要ですが、
身体の動かし方のルールから外れない様に行わなければなりません。
本来であれば、受けの掴み方は皆、同じになります。
手首を掴むという動きでも合理的な動きで行おうとすると、
構造が同じである以上、必然的に同じになるからです。
※筋肉のつき方や体格の違いによって生じる差はあります。
しかし、実際は人により、立ち方や重心の置き方、身体の動かし方の癖があるため、
手首の掴み方一つとっても違っています。
その違いが、身体の動かし方のルールを学ぶ上での障害になっています。
一つの身体の動かし方を学ぶのであれば、可能な限り条件を揃える方が、
学習しやすいことは自明の理です。
そのため、受けの取り方を揃える(個人の癖を無くした動きをする)ことが、
稽古の理想だと思います。
そうすることで、ルールに沿った身体の動かし方を固めることが出来ます。
個別の癖に対応する稽古をするならば、その後に行うべきです。
そうでないとといつまで経っても、ルールに沿った身体の動かし方が固まりません。
人それぞれの癖というのが、稽古の’偏り’になります。
取りの動きも、受けの動きも全て理合に沿って、
合理的に行うと自ずと一つのものになるはずです。
可能な限り、それらの偏り(個人の癖)を取り除くことで、人の違いにより、
惑われることもなく、最短で自分の身体の動かし方を習得出来ると私は思います。
現実には、全ての人の掴み方を統一することは出来ませんので、
上記のことを理解し、自分で人による違いに振り回されない様に
注意して稽古を行なっていくことが重要となります。
流派・会派により合気の定義は違いますので、全ての合気系武道で
当てはまることはありませんが、同じような合気を稽古されている方で、
この記事が参考になる方がいらっしゃいましたら、幸いです。
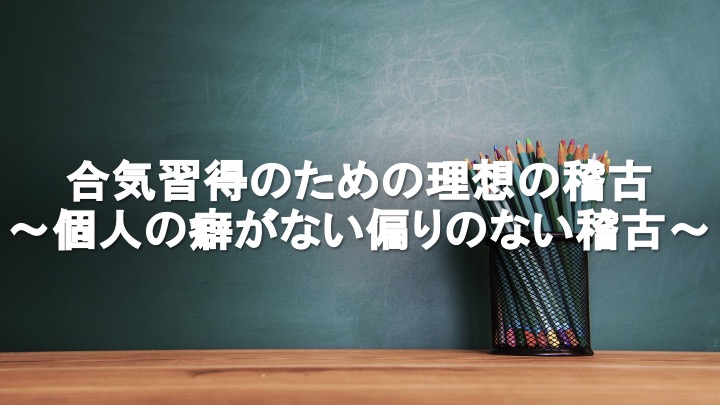


コメント