自分よりセンスがあると思う人が道場を去っていく姿を見ると、
武道の伝承の難しさをまざまざと感じます。
道場を去る理由は人それぞれで、やむに止まれぬ事情があって去っていく人もいる一方、
単に興味が他に移ったという理由で辞めていく人もいます。
私としては、武道は稽古した分だけ奥深い世界を見せてくれるものだと思っていますので、
そこに到達する前に辞めるというのは残念でなりません。
これまでに書いた記事では、’合気’の技を習得することが難しい理由を
私のこれまでの修行で得た知見をもとに書いてきました。
しかし、それらは’合気’特有の理由や技術的な観点から書いたものです。
今回は別の観点から書いてみたいと思います。
そもそもの話、道場の稽古だけで’合気’を習得することが出来るかというと
私は無理だと考えています。
今までに書いた記事の中には、上達するにはどれくらいの頻度の稽古が必要かを論じるものや
’合気’の核となるものを掴むまでに掛かる時間について考察するものがあります。
それらの記事では、正しく稽古していれば週2回程度の稽古をすれば上達しやすいこと、
才のある人であれば、3〜4年の稽古で’合気’の核となるものを掴めると書いてきました。
※上達するのに週2回程度の稽古量があると上達が実感しやすいというだけで、
週1回の稽古や月1回の稽古で上達出来ないと言っているわけではありません。
それは嘘ではありません。
今までに出会い、一緒に稽古してきた人達を見ても間違っていないと考えています。
しかし、これが’合気’を習得するということになると話が変わります。
ここでいう習得というのは、技が身に付き、自然と技が出る状態のことで、
決まった技が出来るということではなく、何をしてくるか分からない相手に対して、
咄嗟に技が出て対応出来るということです。
週2回の稽古だけでも上達出来ますし、’合気’の核となるものを掴むことは出来ます。
しかし、状況に合わせて無意識に技が出るという段階に達するには、
費やす時間が足りない様に感じます。
私の知っている人を見る限り、上達していくにつれ徐々に一人稽古をしたりして、
稽古量が増えていきますので、あくまで入口が週2回程度の稽古ということではないかと思います。
師から教えられる技を習得するというのは、言い換えると、
師の歩んだ道を追体験することだと私は考えています。
指導者は技を伝えるために、可能な限りの工夫をして弟子に教えますが、
稽古という限られた時間だけで全てを伝えることは不可能です。
技のコツや効率の良い稽古方法を教えてもらったとしても、それは技の一部分でしかなく、
それをそのまま受け取っても浅い理解にしかなりません。
稽古中に教えられる内容というのは、弟子が自分で理解を深め、技を習得していくための
きっかけとなるものでしかありません。
そのため、教えてもらったことを自分で咀嚼し、理解を深めるという工程が不可欠となります。
結局、教えてもらうだけでは駄目で、自分で悩み、苦しみ、似たような体験を経る以外に
理解を深めていくことは出来ず、そのためには膨大な時間を費やさざるを得ません。
このあたりが、名人・達人の弟子が必ずしも名人・達人になるわけではない理由だと思います。
天才であってもそれは変わらず、それなりの時間を費やして技を得ています。
勘の良い人であれば、稽古で技を成功させることは難しくないでしょう。
しかし、一度技が出来ることと、それを習得し、自然にその技が出るようになるのは別の話です。
それを為すためにはかなりの熱量が必要となります。
習い事として合気系武道を始める人の多くは、その熱量を持てないために、
’合気’を習得出来ないのではないかと思います。
合気系武道の門を叩く理由は人それぞれです。
不思議な技に魅了されて門を叩く人もいれば、強さを求めた結果として門を叩く人もいます。
はじめる理由は何でも構いませんが、どこかの段階で合気系武道の修行を行うことに
価値を見出せなければ、その熱量を得ることは出来ません。
面白いという理由でも、無形文化としての価値でも何でも構いませんが、
熱量を得るためのものが必要です。
そして、それは内的動機に依存するため、指導者から与えることは出来ません。
個々人で見つけていくしかないものに、’合気’の習得が左右されてしまう。
このことに伝承していくことの厳しさを感じます。
合気系武道は、この20年程で知名度が随分上がり、修行者も増えましたが、
後世に技を残すということで考えると依然として困難な状況が続いていると思います。
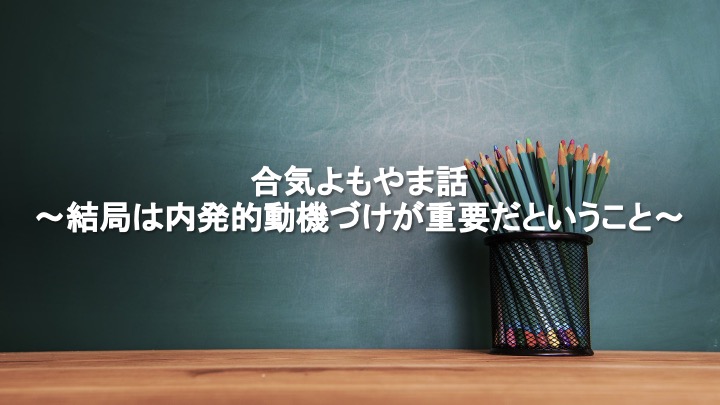


コメント