最近、よく感じることなのですが、簡単に出来る技のコツというのは
求めてはいけないのではないかと思います。
’合気’がどういうものか分かっていなかった頃の話になりますが、
私は稽古している技が相手に上手く掛からず、どうしたら技が掛かるのか
試行錯誤していました。
そうして試行錯誤した結果、それぞれの技の掛け方が徐々に見えてました。
私の場合は時間が掛かりましたが、それでも方向性がたまたま合っていたため、
’合気’がうっすらと見えてきました。
しかし今考えると、これは危険だったと思います。
出来ない技を試行錯誤するのは当然だと感じる方も多いと思いますが、
試行錯誤するにも段階というか、タイミングがあり、その段階に達するまでは
しない方が良いと私は考えています。
私の場合は、入門してすぐの頃から試行錯誤していたため、一歩間違うと
’合気’とは違う方向に行っていてもおかしくありませんでした。
(余計な遠回りをした可能性は否めませんが何とか踏みとどまりました。)
試行錯誤したからこそ分かったこともありますが、
しっかりと指導していただける先生がいるのであれば、
入門して数年は試行錯誤しない方が無難だと感じます。
なぜ入門して数年は試行錯誤しない方が良いかというと、
’合気’の技の全体像を捉えるまでに時間が掛かるからです。
全体像を捉えていない状態で試行錯誤すると明後日の方向に努力してしまい、
最悪の場合、’合気’に辿り着けなくなります。
今まで、稽古で多くの人と出会ってきました。
同じ先生に師事した兄弟弟子達ですが、その中で’合気’を身に付けたのは、
一握りの弟子だけです。
稽古で同じ時間を過ごしたのに、その差はどこから出たのだろうと思います。
一人一人考え方も違えば、感性も違っていますので、気付くものが違うと言えば
それまでですが、私は技への取り組み方や捉え方が違っていたのが
大きいのではないかと感じています。
努力の結果がいつ花開くかは分からないので断言は出来ませんが、
伸び悩んでいる兄弟弟子を見ると、その原因は稽古の初期にある様に思います。
技が上手く出来ない時に、それぞれに技のやり方を模索し、
これが技のコツだというものを見つけてきました。
確かに技にはコツがあり、この様にすれば技が掛かるというやり方があります。
しかし、このコツの捉え方が問題で、’合気’の技の場合はそのコツが
その技だけのコツであってはいけません。
この技ではこれがコツ、その技ではこれがコツという様に別物の場合、
それぞれの技に関連がなく、別の技として存在してしまいます。
(当然ですが、その技は’合気’の技ではありません。)
’合気’の技の場合は、一見違う技の様に見えても、その根底にあるものは
同じでないといけません。
見つけるのは個別の技のコツではなく、’合気’の技に共通する
コツを見つけていくことが重要だということです。
伸び悩んでいる兄弟弟子は、技毎の個別のコツを見つけ、それによって技を構築したために
’合気’の技から遠ざかってしまったのだと思います。
一度考えが固まるとそれを修正することは中々出来ません。
稽古の初期に間違った技の捉え方で固定してしまうと、すぐに頭打ちとなってしまいます。
これに関しては、これまでの記事でも書いている様に正しく受けを取れないために、
正しく’合気’の技が理解出来ないということも関係していますが、
やる気に満ち溢れた入門初期の過ごし方が与える影響の大きさも物語っています。
入門初期には、試行錯誤するのではなく、師から指導されることだけをやる。
これは消極的にも見えますが、武芸を修めるために大切なことだと思います。
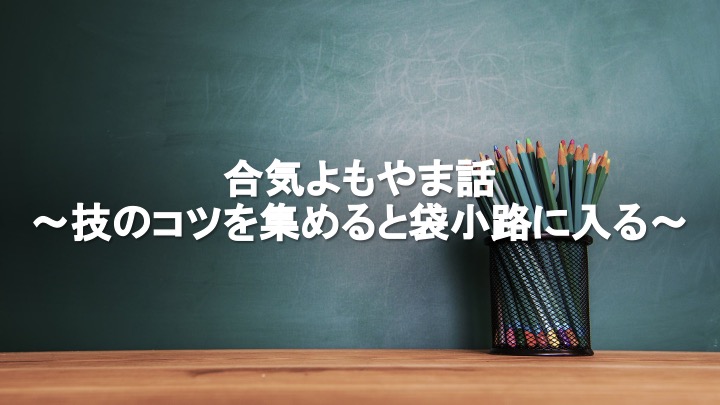


コメント