’合気’という技法は、ある種理不尽な面があり、
数年の修行で’合気’の手掛かりを得られる人がいる一方、
長年修行に明け暮れても、’合気’の手掛かりを得られない人もいます。
あまりの理不尽さに、この差はどこからくるのかよく考えます。
長年修行していても、’合気’を取れないというのは、様々な理由があるのだと思いますが、
その差はどこから来るのでしょうか?
今回は、私が考える理由について、書いてみたいと思います。
私もそれほど多くの流派を学んだわけではないので、これは私の所感になりますが、
合気系武道には’オタク’気質の方が多い様に思います。
かくいう私も、そんな一人です。
自分が学んでいる流派の修行も中途半端なのに、ついつい他流派の技についても
気になってしまい、調べてしまいます。
典型的な武道オタクと言っていいでしょう。
長年修行しても、’合気’が取れない理由ですが、一つは’オタク’であることが
原因になっていると思います。
現代では、SNS上で様々な流派の技が公開され、解説されています。
それらの動画では、身体操作やある種のコツが紹介されています。
私のような、’オタク’気質の人間は、ついついそれらの情報に飛びついてしまうのですが、
おそらく、それが良くありません。
武道・武術の技は、そもそもそんな身体操作やコツで出来るものではありません。
繰り返し繰り返し同じ動作を行うことで、意識して行っているものを
無意識で行える様にしてはじめて出来るものです。
過去の自分を振り返ると恥ずかしくなりますが、色々な書籍を読み漁り、
その知識で何とか出来ないかと右往左往していました。
私のような’オタク’気質な人が、’合気’を取れないのは、効率よく習得したいと考えて、
技のコツを求め、いつまでも頭で考えて行なう稽古から脱却出来ないのが原因だと思います。
頭で考えて行なっているうちは、それは稽古になっておらず、
咄嗟に技が出るよう無意識に落とし込む段階に移ってからが本当の稽古です。
また、’合気’を習得するには、自分の身体の状態を変える必要がありますが、
そのために必要な稽古も、同じ動作を繰り返し繰り返し行うことです。
新しいものに興味が移り、その研究にうつつを抜かして、
基礎を固める稽古に力が入らないのもよくないのだと思います。
合気系の武道では、’相手を受け入れる’ように指導されることがよくあります。
この意味もよくよく考えるととても深いものがあります。
テクニックとして、’相手の力をもらう(受け取る)こと’を
’相手を受け入れる’と表現していると考える人も多いと思いますが、
下記の様な考え方も出来ます。
’合気’の技を行う場合、自分の身体から余計な力が抜けている必要があります。
これはそもそもとても怖いことです。
人が防御する際の反応としては、筋肉が緊張する方が自然な反応です。
そのため、身体の力を抜くという行為は、意図して行わなければいけません。
’合気’の技では、向かってくる相手に対して、身体の力を抜くという行為を
自分の意思で行わなければいけないわけですが、その状態は向かってくる相手に対し、
自分の無防備な状態を晒すということであり、とても恐怖を伴うものです。
そのため、恐怖に打ち勝つことが’合気’の技を行うための条件となります。
つまり、’相手を受け入れる’とは、恐怖により身体を固めて
相手を拒絶してはいけないということを言っているわけです。
それを行うためには、必然的に弱い自分と向き合わなければいけなくなります。
恐怖に打ち勝たねばいけないというのは、どの武道・武術にも共通している
ことだと思いますが、’合気’という技法に目が眩み、
私のようにそれが見えなくなっている人も多いのではないかと思います。
恥ずかしい話ですが、私は、’合気’はテクニックがあれば、出来るものだと考えていました。
精神修養の大切さに気付かず、目先の技術にばかり目を奪われていたことが、
長年私が’合気’を取れなかった理由だと思います。
以上のことから、’合気’を取れる人と取れない人の差は下記の違いにあるのではないかと
私は考えています。
・目先のテクニックではなく、自分の身体の状態を変え、
無意識に動ける様になるような基礎に主眼を置いて稽古しているか
・自分の恐怖に打ち勝つための精神修養を伴う稽古をしているか
ついついノウハウを求めてしまう私のような、’オタク’気質な人間には中々辛い話ですが、
何事も本質は変わらず、基礎をしっかり行うことが大切なのだと思います。
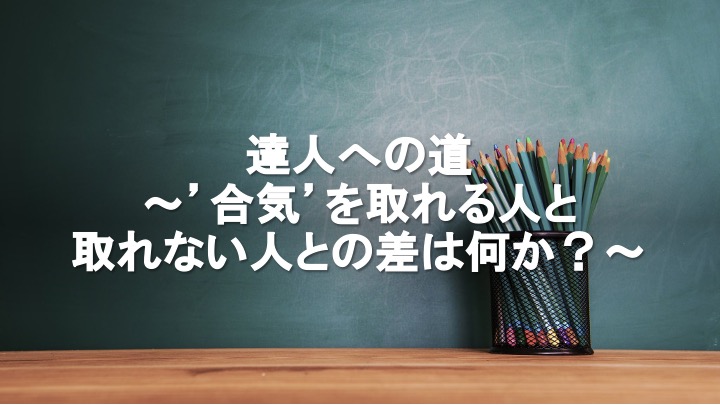


コメント