’合気’を習得するための稽古には、守るべきルールが存在していると私は考えています。
そのルールは、指導者や先輩によっては、きちんと言葉で指導されることもありますが、
私の今までの経験では、基本的には暗黙のルールとして存在しているように思います。
今更言葉で説明するようなものではないという思いと、言われなくても気付く人は気付くし、
気付かない人は、言葉で言われたところで理解出来ないという諦めから、
そのような状況となっているように感じます。
私が学んでいる流派の稽古は、掛かり稽古を主としていますので、
これから書くことは、掛かり稽古についてのルールとなります。
大前提:稽古は技を学び、身につけるためのもので、実戦ではない。
この前提については、恥ずかしながら、私も以前は理解出来ていませんでした。
掛かり稽古で行なっている技をそのまま実際に使えるものだと考えており、
実戦で使うためには、こうでなければ使えないなどと自分で勝手に想定を作り、
その想定に囚われていました。
確かに、実戦でそのまま使える技もありますが、そのように考えてしまうと
相手を倒したり、投げることに固執してしまい、結果的に技を学ぶことが出来なくなります。
’合気’の技は、最終的には技に形が無くなり、動けば技になるというものだと私は考えています。
そのため、一つの形に拘り、それで何とかしようとすることに意味はありません。
実戦を想定するということは大切なことですが、稽古は実戦とは違うという前提は
忘れてはいけないと思います。
受けが取りに掛かっていく時は、指定された通りに掛かっていく。
同じ条件で繰り返し稽古することで技が身につきます。
様々な条件の稽古をすることで、全てに対応出来るようにするという
考え方もあると思いますが、’合気’は形の定まったものではないため、
そのような稽古を行うと’合気’を習得する難易度が上がってしまいます。
そのため、条件は可能な限り揃える必要があります。
まれに意地悪したり、相手を試すために、掴み方やタイミングを
変えたりする人がいますが、それを行なっている人の自己満足でしかありません。
手首の掴み方等、個人の癖を可能な限り排除して、揃えることが大切です。
また、相手に掴みに行った際に、体勢が崩れている人がよくいますが、
技を掛ける前から体勢が崩れていると正しく技が掛かっているか
分りませんので、体勢が崩れないように掛かって行くことも必要となります。
受けが取りに掛かっていく時は、掛けられる技を知らない体で掛かっていく。
掛かり稽古の場合、受けが順番に取りに掛かっていきますので、
自分の前に掛かっていく人を見ることで、どのような技を掛けられるか、
事前に知ることが出来ます。
そのため、中にはわざと身体を逃して技が掛からないようにしたり、
技が掛かっていないのに受身を取る人がいます。
そのようなことをしても稽古にはなりませんので、
掛かり稽古では、受けは自分が掛けられる技を知らない体で、
取りに掛かっていき、技がきちんと掛かってから受身を取らなければいけません。
受けが取りに掛かっていく時は、きちんと意識を取りに向ける。
掛かり稽古は、機械的に順番に受けが取りに掛かっていくため、
取りに意識を向けずに掛かっていく人が一定数います。
’合気’は、意識が向いていないと掛かりにくい性質がありますので、
稽古を成立させるためには、受けはしっかりと取りに意識を向けて
掛かっていく必要があります。
取りが技を掛ける時は、技に要求される通りの動きで技を掛ける。
技に要求されていない動きで相手を倒したり、投げたりしても、
稽古としては意味がありません。
ムキになって力で相手を倒したり、投げたり人がいますが、
感情的にならずに、技に要求される動きを丁寧に行なって、
技の稽古を行うことが大切です。
掛かり稽古では、上記の内容を守って稽古することで、
初めて稽古として成立すると私は考えます。
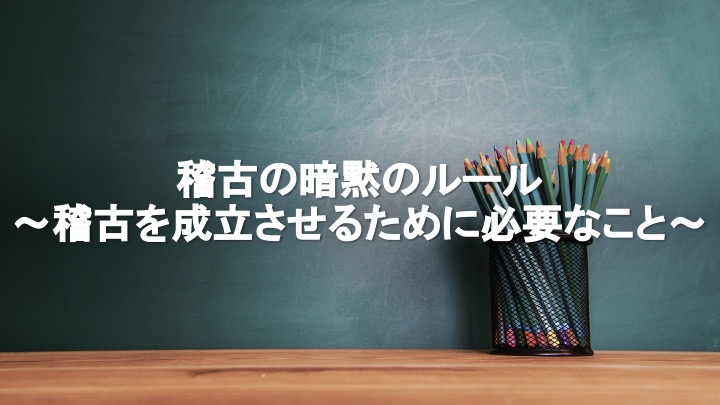


コメント