今日は私が学んでいる合気系武道について、書きたいと思います。
合気の定義については、流派・会派により違っていますので、
今回、私が書く内容は全然違うと思われる方もいらっしゃると思いますが、
そこは流派・会派の違いだと考え、ご容赦ください。
合気系武道の特色の一つとして、技の数がとても多いということが挙げられます。
YouTubeで合気系の動画を見るだけでも、かなりの数の技が見て取れます。
では、なぜそんなにも多くの技が存在するのでしょうか?
技の中には、相手に後ろから襟を掴まれて、投げるというような技もあります。
後ろから襟を掴まれることも想定し、技が作られているということでしょうか?
実戦では、相手がどこを掴んでくるか分かりませんので、
想定し、備えるということは大切だと思いますが、
実際に後ろから襟を掴まれる確率は低く、
それを稽古する意味はあまり無いように感じます。
では、なぜ色々なシチュエーションの技を稽古するかといえば、一つ一つの技をそれぞれ
覚えるのではなく、それぞれに共通した身体の使い方や意識の使い方を学ぶためだと思います。
そのため、百個の技があったとしても、感覚としては一つの技を稽古していると感じます。
確かに、掴まれた部位や掴まれ方により、コツのようなものは存在しますが、
個別の技ではなく、同じ技です。
技の外見は違っていても、全て同じ技です。
合気系武道にも様々ありますが、そのように考え、稽古する流派がありますので、
ご紹介させていただきます。

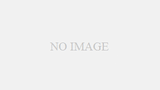
コメント