振り返ると今まで行なっていた稽古で駄目だったと思うものがあります。
合気系の武道では合気上げという稽古があります。
自分の手首を相手に両手で掴んで押さえてもらい、
押さえ込まれている手を上げるという稽古です。
相手に力一杯持たれると、押さえ込まれている手は
中々持ち上げることが出来ません。
そのような手を上げることが困難な状況であっても、
手を上げることが出来るように技を練るという稽古です。
若い頃の私は、相手に思いっきり持ってもらった状態で
手を上げることが出来なければ意味が無いと考え、
入門して間がない頃から、相手に全力で手首を押さえてもらっていました。
当然、相手の手に力が入っていますから、
その力に反応して自分も力んでしまっていました。
上級者であれば、相手に力が入っていても反応せずに
力まずに合気上げを行うことが出来たと思いますが、
初心者の私には出来るはずがありません。
結果は相手の力に反応して力むという悪い癖がついただけでした。
何事もそうだと思いますが、余計な力が入っている状態では
何をやっても上手くいきません。
技を練る稽古で、無駄に力むという悪癖がついた私は
中々技を身につけることが出来ず、また、今でもその悪癖に悩まされています。
今考えると入門したての時には、相手に加減をして手を持ってもらい、
技としての合気上げを身に付けてから、徐々に段階を踏んで
力を入れて押さえてもらうという稽古をするべきだったと思います。
何事も段階というものがあり、一足飛びに事を成すことは出来ません。
何気なく行なっている動作でも繰り返し行なっていると癖になり、
意図せぬ動きが身につきます。
私が思うに稽古は良い癖を身に付けていくためのものです。
良い癖を身に付けていった結果、技が無意識に出るようになる。
これが目指すべき姿です。
技がどういうものか理解した上で、良い癖だけが付くように
稽古を丁寧に丁寧に行っていく。
理想はあっても、それを最初から行うのではなく、
段階を分けて、理想に近づけるように稽古を行なっていくことが大切だと思います。
この記事が何かしらのお役に立てれば幸いです。

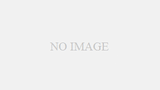
コメント