武道・武術では、型を稽古することにより、
正しい身体の使い方を身につけていきます。
私は型稽古無しに武道・武術の上達はないと考えています。
型稽古をしないように思われている流派であっても、
突きや蹴りなどの基本は繰り返し行なっています。
フォームを確認しながら、突きや蹴りを行った場合、
それは型の稽古を行なっていることと変わりありません。
では、同じ型を稽古していたとして、得られるものは皆同じなのでしょうか?
基本の動作が身についたとして、それは皆同じもので、
違いは稽古の進み具合によって生じる差だけなのでしょうか?
その点に関して、私は違うと考えています。
それぞれ目指すところがあって、稽古しているわけですが、
型に対する考え方や目指すところが違っていると
それぞれ得るものが違っているように思います。
型という、決まった動作であっても、そこに何を見出すかは人によって違っており、
それは個人の目指すところや考え方によって生じているように思います。
突きという同じ動作でも、スピードを求める人であればスピードを、
威力を求める人であれば、威力を、
スピードとパワーが無くても避けられない突きを求めれば、そのような突きを、
という具合に個人が求めるものをその動作に見出していきます。
個人が求めるものが見つけられるので、ある意味夢のような話です。
正しく求めて、正しく稽古すれば、それが手に入ります。
個人の理想が叶えられるという点では、何ら不都合が感じられないかもしれません。
しかし、流派の技を伝承するという場合には、話が変わってきます。
流派の技を伝えるために型があると思うのですが、
型稽古を行って身につくものが個人により違うというのであれば、
技の伝承を行うことは出来ません。
そのため、型だけが残っていても意味がなく、
正しい解釈がセットになっていることが不可欠となります。
私は師の技に憧れて、現在学んでいる流派の技を長年稽古してきました。
私と同じような経緯で、道場に入門された方も多くいますが、
そこで身に付いているものはそれぞれ違っています。
その差は、上記に述べた理由により生じていると思うのですが、
同じように師の技に憧れて稽古に励んでいるにも関わらず、
結果が違っているということに対しては思うところがあります。
型稽古を行う場合は、何を目指すのか、どのようになるのが正しいのかを
しっかりと自問自答しながら稽古を行うことが大切です。
そうしなければ、道場に通い、その流派の技を習っているにも関わらず、
全く違う技を稽古しているということになりかねません。
私自身も、きちんとそのあたりを踏まえて稽古をしないと
間違った方向に行ってしまう可能性がありますので、
しっかりと自問自答を繰り返して、稽古に励みたいと思います。
この記事が何かしらのお役に立てれば、幸いです。

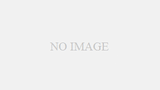
コメント