合気の技を稽古している時、技の成否の判断基準の一つとして、手応えの有無があります。
合気の技の場合、自分に手応え(力感)があれば、その技は失敗しています。
ただの力技と判断出来ます。
合気の技を行なっている時に、手応えがないのは、次の理由に拠ります。
1.相手と力がぶつかっていないために、押したり引いたりしていない。
(これは自分と相手を同調させる等の技巧を通して行います。)
2.腕力ではなく、身体の力を使っているために、力感を感じない。
昔、読んだ書籍の達人の言葉に、’羽織を羽織るようにして人を投げる’とありましたが、
手応えを感じずに人を投げるというのは、これに通じるものを感じます。
手応えを求めないという点が、日常生活で行なっている動作との大きな違いではないでしょうか?
日常では、物を持つにしても重さを感じた上で、しっかりと手応えが有る動作を行なっています。
そのため、物の重さを無視して動くというのは、合気を習得するための一つの稽古に成り得ます。
合気の技の稽古を行なっている時に少しでも手応えを感じたなら、
それを徹底的に無くす方向で稽古すると良いと思います。
日常の動作とは異なるため、はじめはどのように動いたら良いか分かりませんが、
そこで流派の技の教えをもとに試行錯誤することにより、合気の技に近づくことが出来ます。
技の手応えが無いというのは、技が成功したという実感に乏しいものです。
不安に思い、無意識に手応えを求めてしまいますが、
そうするといつまで経っても合気の技には近づくことは出来ません。
その不安をグッと抑えて、手応えの無さを求めることが大切で、
そのような稽古を繰り返し行うことで、いつしか手応えの無いことが当たり前となり、
手応えの無いことに不安を感じることが無くなります。
日常の動作を非日常の動作に変え、それを不思議とも何とも思わなくなる。
それが稽古のあるべき姿なのではないかと思います。
この記事が何かしらの助けになれば、幸いです。
※合気の定義は流派により違いますので、この記事の内容が合致しない場合は
ご容赦ください。
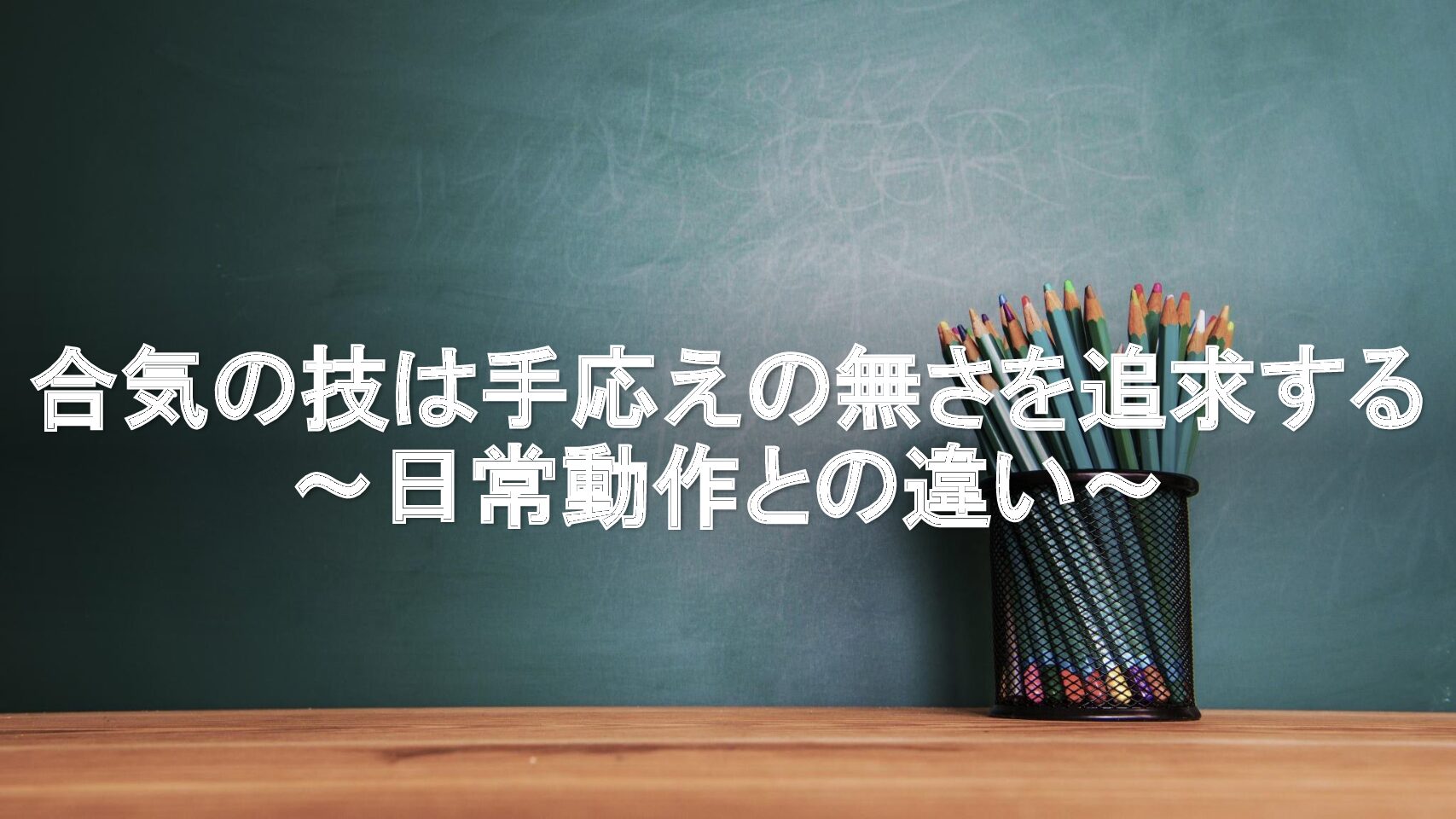

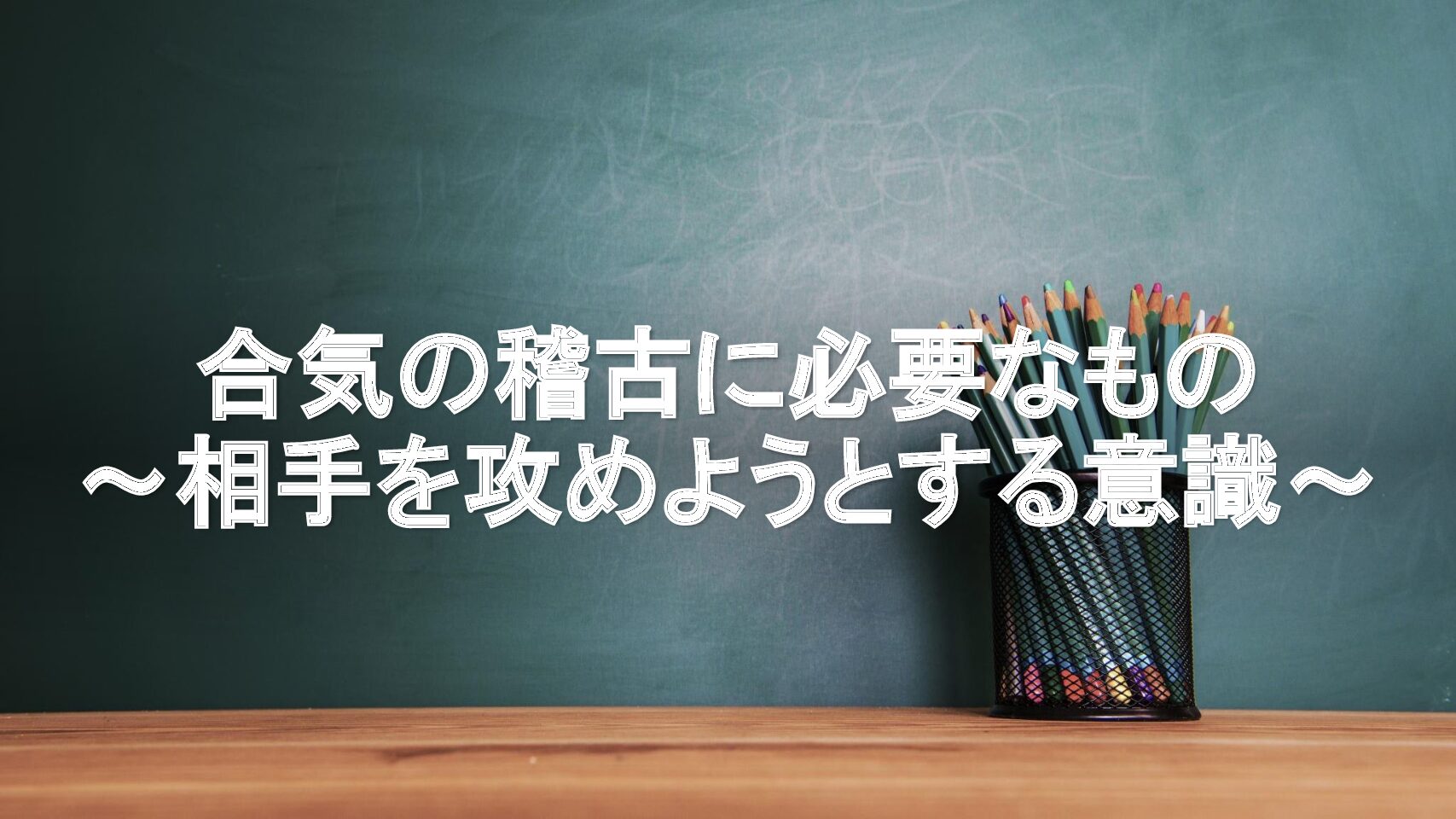
コメント